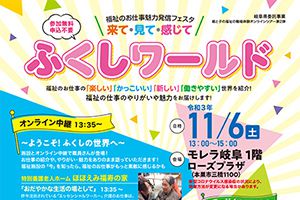「福祉の職場体験オンラインツアー」開催レポート
update 2022/09/05

「認定制度普及促進説明会」開催レポート
update 2022/07/19

【開催日:6/9】岐阜県介護人材育成事業者 認定制度普及促進説明会開催
update 2022/05/26
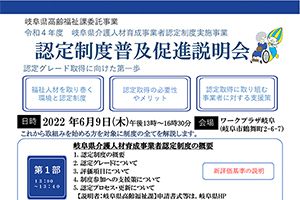
【開催日:6/11】福祉のお仕事フェア in 岐阜地域 開催 (予約制、当日予約可)
update 2022/05/26

ぎふ・いきいき介護事業者「認定証授与式&記念講演会」開催レポート
update 2022/01/07

令和3年度 ぎふ・いきいき介護事業者が決定!
update 2021/12/24
オール岐阜・企業フェス・オンライン開催のお知らせ
update 2021/11/25

「認定事業取り組み事業者セミナー&交流会」開催レポート
update 2021/11/17

介護に関する入門的研修
update 2021/10/27

福祉お仕事魅力発信フェスタ 来て・見て・感じて ふくしワールド
update 2021/10/18